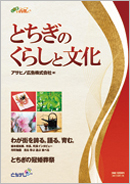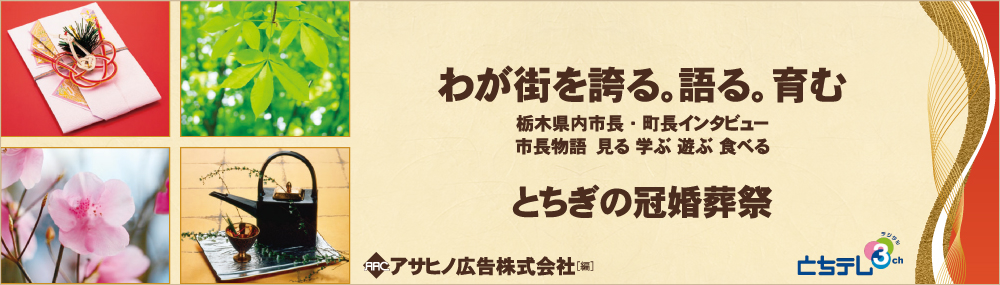お墓を建てる
墓地の種類は大きくわけて、寺院の墓地・公営の墓地(霊園)・民営の墓地(霊園)の3種類です。寺院の墓地は故人が檀家である場合にのみ利用できます。
公営墓地は各都道府県の自治体が管理運営しており、宗教・宗派は問いません。
民間の墓地は民間企業のほか、財団法人や宗教法人が管理運営しており、施設面では充実しています。
家単位のお墓にこだわらず、共同の納

骨堂を持つ永代供養墓や共同墓を選ぶ人も増えています。また最近では墓石の代わりに木を植える樹木葬や散骨をする人も見られます。
自宅の祭壇に安置していた遺骨は、四十九日の法要を過ぎると墓地に納骨されるのが一般的です。しかし、納骨の時期には決まりはなく、葬儀の当日や初七日に行われるケースもあります。新しくお墓を作る場合、一周忌から遅くても三回忌には間に合うよう準備したいものです。
お墓にかかる費用は次のように分類されます。
墓地使用料
墓地の経営者に支払う使用料です。
年間使用料
墓地の1年間の維持管理費にあたるものです。
墓石建立費
墓石とその建立に際してかかる費用です。石材の種類やお墓の規模によって価格は様々です。
お布施(入檀料)
その寺院の檀家ではない場合、入檀料を払って檀家となります。
新しくお墓が完成すると、埋葬時に僧侶を招いて開眼供養を行い、故人の魂を迎え入れます。一周忌やお彼岸、新盆に合わせて行う場合もあります。
納骨式は家族だけで営まれ、お墓が既にあるときは忌明けの法要で納骨をします。新しくお墓を建てた場合は開眼供養とともに納骨式を行います。
神式では火葬後すぐに納骨することになっていますが、自宅に持ち帰る場合は五十日祭までに納骨をします。納骨に際しては埋葬祭が営まれます。
カトリックは葬儀から1カ月後の追悼ミサの日に、プロテスタントでは1カ月目の昇天記念日に、神父や牧師の立ち会いのもとで納骨します。
お墓には命日やお盆、お彼岸にはお参りに行きましょう。その際は墓石の掃除や草むしりなども行い、お花やお線香を供えます。