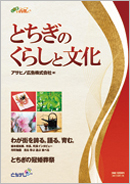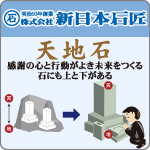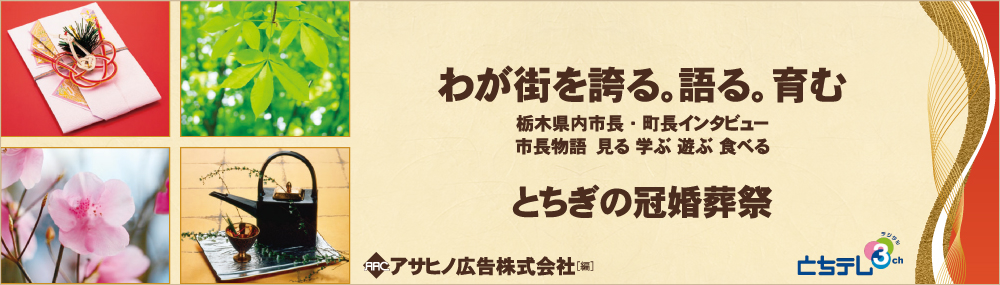神前結婚式
神前式は1900(明治33)年に大正天皇の成婚を記念して行われた挙式が始まりで、歴史は比較的新しいスタイルです。式に参列できるのは基本的に親族だけですが、ホテルや結婚式場に併設されている神前式場の中には、会場内に別に座席を設けて親族以外でも参列できるところもあります。
入場
巫女の先導により新郎と媒酌人、新婦と媒酌人夫人、新郎の両親、新婦の両親、新郎の兄弟親族、新婦の兄弟親族と続いて入場します。神前に向かって右側に新郎側、左側に新婦側が着席し、媒酌人は新郎新婦の後ろに着席します。
斎主入場
一同が着席すると、斎主が入場します。


写真提供:二荒山会館
修祓の儀(しゅばつのぎ)
全員起立して頭を下げ、斎主によるお祓いを受けて身を清めます。
祝詞奏上(のりとそうじょう)
斎主が二人の結婚を神に報告し、守護と両家の繁栄を祈る祝詞を奏上します。
一同起立し、頭を下げて祈ります。
三献の儀(三三九度)
新郎新婦が夫婦の契りを固める儀式です。大中小三つの盃でお神酒をいただきます。一の杯(小)は新郎から新婦、そしてまた新郎へ。二の杯(中)は新婦から新郎、新婦の順に。三の杯(大)は新郎、新婦、新郎の順にいただきます。お酒が飲めない場合は口をつけるだけでもかまいません。
誓詞奏上(せいしそうじょう)
新郎新婦が神前で誓いの言葉を読み上げます。誓詞は新郎が読み上げ、最後に新郎が自分の名前を言い、続いて新婦も自分の名前を言います。
玉串奉奠(たまぐしほうてん)
挙式が無事終了したことを感謝し、神前に玉串を供える儀式です。
新郎新婦から捧げ、続いて媒酌人夫妻、両家代表者の順に行います。
指輪の儀
指輪の交換を行う儀式です。まず新郎から新婦に。そして新婦から新郎の指にはめます。玉串奉奠の前に行う場合もあります。
親族盃の儀
斎主の合図により、列席者(親族のみ)一同がお神酒を飲み干し、親族関係を固めます。杯は三回に分けて飲み干します。
舞楽奉納
式場によっては巫女舞を行う場合があります。
斎主一拝
斎主による祝詞が述べられ、式が終了します。
退場
一同神前に一礼し、斎主の退場後、入場と同じ順番で退場します。当日は式の直前に式次第の説明がありますので、式場担当者の案内に従って行いましょう。