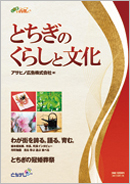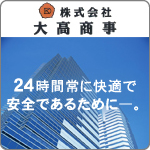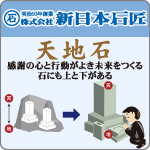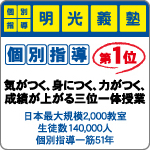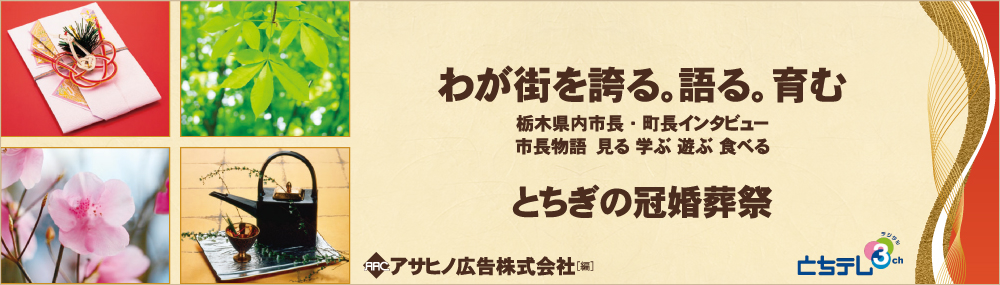大人のお祝い事
成人式は貴族の「加冠の儀」や武家の「元服の儀」に由来するとされ「冠婚葬祭」の「冠」を意味する重要なお祝いです。1948(昭和23)年に成人の日が国民の祝日と制定されると、国民的行事として祝うようになりました。
満20歳を迎えた男女は選挙権が得られ、結婚も本人の意思により自由にできるなど、法律的にも権利が認められます。同時に社会的な義務と責任も負うことになるため、社会人としての自覚が求められます。
そのような意味で成人のお祝いは子ども時代のお祝いとは異なるため、大人としての自覚を促し記念となるものがよいでしょう。基本的には身内でお祝いをします。
記念の品は、成人式を迎える時に、学生なのか社会人として勤め始めているかにより配慮します。
学生であればこれから必要となるスーツやネクタイ、ネクタイピン、アクセサリー、時計などもいいでしょう。
現金や商品券などを贈る場合、親族からであれば1〜2万円が目安です。
また、品物に限らずホテルでの食事や観劇、音楽会などといったフォーマルな社交場へ一緒に伴うのも大人への一歩としてよい経験となるでしょう。
成人式の服装は、和装の場合未婚女性の第一礼装である中振袖に袋帯を締めます。母親の持っているものを譲り受けて着るのも好ましいものです。洋服でもよく、アンサンブルやワンピース、スーツなどがよいでしょう。
男性は和装ですと黒紋付羽織に袴が正礼装です。洋装ならスーツがよいでしょう。しかし、成人式の服装に特に決まりはありませんので、正礼装に無理にこだわらず、自分にとって晴れの日にふさわしい装いがよいでしょう。
大学や専門学校などを卒業すると、いよいよ名実ともに社会人の仲間入りを果たします。お祝いには社会人として必要となるものや、装身具など記念にもなるものを贈ると喜ばれるでしょう。
具体的には男性の場合はスーツ、ネクタイ、ネクタイピンや時計など。女性ならスーツやバッグ、時計やアクセサリーなどもよいでしょう。当人の好みがありますので商品券や現金で渡す方法もあります。
家との結びつきを重要視してきたかつての日本には結婚記念日を祝うという習慣はありませんでしたが、明治に入って欧米で行われている結婚のお祝いが次第に一般化してきました。
欧米では結婚1年目には紙婚式、そして60年目にはダイヤモンド婚式というように節目の年に記念になるものがあり、それにちなんだものを記念に贈るといった習慣があります。しかし、これにとらわれる必要はなく、夫婦で記念の食事をしたり節目ごとに記念写真を撮るのもいいでしよう。
結婚25年目の銀婚式と50年目の金婚式は特別なお祝いですから、親子や孫など親族が一緒にお祝いし、食事会や写真撮影、旅行などを企画するのも喜ばれることでしょう。

写真提供:田村写真館

写真提供:田村写真館


写真提供:日本蘭科植物園
| 1年目 | 紙婚式 |
| 2年目 | 綿婚式 |
| 3年目 | 革婚式 |
| 4年目 | 花婚式 |
| 5年目 | 木婚式 |
| 6年目 | 鉄婚式 |
| 7年目 | 銅婚式 |
| 8年目 | 青銅婚式 |
| 9年目 | 陶器婚式 |
| 10年目 | 錫婚式 |
| 11年目 | 鋼鉄婚式 |
| 12年目 | 絹婚式 |
| 13年目 | レース婚式 |
| 14年目 | 象牙婚式 |
| 15年目 | 水晶婚式 |
| 20年目 | 磁器婚式 |
| 25年目 | 銀婚式 |
| 30年目 | 真珠婚式 |
| 35年目 | 珊瑚婚式 |
| 40年目 | ルビー婚式 |
| 45年目 | サファイア婚式 |
| 50年目 | 金婚式 |
| 55年目 | エメラルド婚式 |
| 60年目 | ダイヤモンド婚式 |
| 75年目 | プラチナ婚式 |
長寿のお祝いは「賀寿」と呼ばれ、長寿を祝って行います。
十二支十干が一回りして再び生まれた時と同じ干支である満60歳、数え年で還暦の61歳よりお祝いをしますが、最近は還暦といっても定年後に働く人や第二の人生を謳歌する人も多く、皆元気で若々しいので老人扱いするのは失礼にあたるでしょう。長寿のお祝いとしては古希を始まりとするのがよいかもしれません。
お祝いの品には古来より赤いちゃんちゃんこを贈る習わしがありますが、赤いシャツなども一案です。しかし赤いものにこだわる必要はありません。
衣類や実用品など当人に喜ばれる品物や家族との食事会、旅行のプレゼントなども喜ばれるでしょう。
還暦(かんれき) 六十一歳
十二支十干が一巡して生まれた年の十二支十干が巡って来る年が還暦。
古希(こき) 七十歳
中国の詩人、杜甫の詩にある「人生七十古来稀也」という句に由来する。
喜寿(きじゅ) 七十七歳
「喜」という漢字が草書体が七十七に見えることに由来する。
傘寿(さんじゅ) 八十歳
傘の略字が八十に見えることに由来する。
米寿(べいじゅ) 八十八歳
「米」という漢字を分解すると八十八に見えることに由来する。
卒寿(そつじゅ) 九十歳
「卒」の略字「卆」が九十に見えることに由来する。
白寿(はくじゅ) 九十九歳
「百」という漢字の上にある一をとると「白」になることに由来する。
百歳以上は毎年お祝いをします。
病気やけがで療養中にお見舞いを頂いた方には、快復後にお礼状と快気内祝いの品物を贈ります。
品物はお見舞いの額の2分の1〜3分の1を目安にし、お見舞いを頂いた方には一律で同じ品物でよいでしょう。
病気やけがが「治る」という意味をかけて、後に残らない洗剤や石鹸、砂糖やお茶などの食品が一般的です。
水引は紅白の結びきりです。表書きは「快気内祝」とします。
親しい人や仕事などでお世話になっている人がお店を開店・開業した時には、心からのお祝いをしたいものです。
贈り物は花輪やアレンジメントなどが一般的ですが、品物を贈る場合には時計や傘立て、観葉植物なども挙げられます。好みもありますし品物が重複しないよう、選定にあたっては相手の希望を聞いたほうがよいでしょう。なお、開店、新築のお祝いにはライターや灰皿など「火事」を連想させるものはタブーですので気をつけましょう。
現金を贈る場合は身内、友人いずれも1万円が目安です。祝儀袋への水引は紅白の蝶結びで熨斗をつけます。表書きは「祝御開店(開業)祝」「祝御開店(開業)」とします。
開店にあたり、オープニングパーティーに招待された場合はできる限り出席しましょう。やむなく欠席する場合は祝電やお花などを贈ります。
身内や親しい間柄の人から新築完成・披露のお知らせを受けたら、お祝いを贈ります。最近はリフォームなどの増築工事もしばしば行われていますが、小規模な工事ならあえてお祝いは贈らず、大規模なリフォームを行っているようでしたら新築に次ぐお祝いをしてもよいでしょう。
お祝いの品物は、時計等のインテリア用品なども挙げられますが、新しい住まい作りのイメージを尊重し、希望を聞いてから贈るとよいでしょう。やや高額な品物でしたら友人と合同で贈るという手段もあります。なお、火事を連想させるライターや灰皿などの品物はタブーです。
新築披露が行われる場合、先方へ伺う時までに品物が届くように手配します。
現金で贈る場合の金額の目安は、身内なら1〜1万5000円、友人であれば1万円くらいです。知人の間柄でしたら5000円程度です。
祝儀袋の水引は赤白の蝶結びで熨斗をつけます。表書きは「御新築祝」「祝御新築」「御祝」と書きます。
国から勲章や褒章を授けられることを「受章」と表し、国以外の民間組織などから表彰された場合には「受賞」といいます。当人が受章や受賞の通知を受けたら、関係者やお世話になった方々にすぐ知らせます。お祝いや祝電を頂いた方の記録をしておき、後日改めてお礼をします。
知人の受章・受賞の通知を受け取ったら祝電などでお祝いの気持ちを伝えます。受賞通知後すぐは電話の対応に追われていることが予想されますので、親しい間柄でない限り電話は避けたほうがいいでしょう。
お祝いの品を贈る場合には1週間〜10日以内に届くよう手配します。
品物はお花やお酒などが一般的です。
祝賀会が開かれる場合にはお祝いを持参します。金額は1万円が目安です。品物はかさばるので持参するのは避けましょう。
プロに限らず、趣味や勉強の成果を発表して見てもらうことは今後の励みにもなります。発表会や展覧会の案内を受けたら、できる限り足を運ぶことが一番のお祝いとなります。
案内状を送る際には、先方が負担に感じないよう無理に誘わず「ご都合がよろしければ…」程度に書き添えるにとどめます。
ご案内状を受け取ったときは、友人や知人なども誘って伺うとよいでしょう。
当人に作品の感想などを伝えると今後の励みになります。
心遣いとしてお菓子や飲物などの手土産を持参すると喜ばれます。
お花を送る場合は開催初日に間に合うように贈ります。花束は避け、花器に移し替えずそのまま会場に飾れるアレンジメントがよいでしょう。